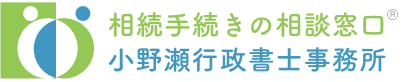任意後見制度と法定後見制度の違い【相続手続きの相談窓口】
【法定後見制度】
☆認知症になったときに利用できるのが→法定後見制度
法定後見とは、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
法定後見には、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
成年後見:本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助:本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。
【任意後見】
☆認知症になる前に備えておくのが→任意後見
任意後見とは、判断能力があるうちに、公正証書を作成して任意後見契約を結び、判断能力が低下したときの事務(財産管理や療養看護に関する事務)の内容と、後見人になる人を定めておく制度です。
任意後見制度の基本理念は、利用者の「自己決定権の尊重」です。
「任意後見と法定後見の関係は?」
任意後見契約が登記されている場合は、原則として、任意後見契約が優先される。
1.任意後見と法定後見の調整
任意後見は本人の意思に基づく支援制度であるから、任意後見と法定後見とでは任意後見が優先します。
任意後見の登記があり両者が競合する可能性がある場合には、裁判所は、法定後見による支援が「特に必要」かどうかにより判断します。
具体的には次の2.3.の通りです。
2.任意後見監督人が申立てされた場合
先行する法定後見がなければ、裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見が開始します。
既に法定後見が開始しているときは、裁判所は、当該法定後見を継続することが「特に必要」かどうかを審査します。
「特に必要」と認めるときは任意後見監督人選任申立てを却下し、法定後見を継続します。
「特に必要」と認められないときは、任意後見監督人を選任し、先行する法定後見を取り消します。
3.法定後見の申立てをされた場合
任意後見の登記がなければ、そのまま法定後見の開始要件を満たすか審査し、待たすと判断すれば開始の審判をします。
任意後見の登記があるが、任意後見監督人がまだ選任されていないときは、法定後見による支援が「特に必要」か審査し、「特に必要」と認めるときは、法定後見開始の審判をします。
このとき任意後見契約は終了せず、後に任意後見監督人選任の申立てがなされる余地が残ります。
「特に必要」と認められないときは、法定後見の申立てを却下します。
既に任意後見監督人が選任されているときも、法定後見による支援が「特に必要」かどうかを審査し、「特に必要」と認めるときは、法定後見開始の審判をし、任意後見は当然に終了します。
「特に必要」と認めないときは法定後見の申立てを却下し、任意後見が継続します。
4.「特に必要がある場合」とは?
一般には、任意後見の代理権の範囲が本人の保護のために不十分である場合、本人のおかれている状況からして同意見・取消権による保護を必要とする場合が考えられます。
これに加え、合意された任意後見人の報酬が不当に高額である場合、受任者に不適格事由がある場合、本人が法定後見を選択している場合などがあげられます。
また、法定後見申立てに対する対抗的な任意後見契約につき、受任者の「公平らしさ」に問題がある等として監督人選任を却下し法定後見を開始した例もあります。
 小野瀬行政書士事務所は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の任意後見に関する相談を承っております。
小野瀬行政書士事務所は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の任意後見に関する相談を承っております。
任意後見のメリットとその限界とは?【相続手続きの相談窓口】
「任意後見のメリット」
自分に対する支援者(任意後見人)と支援の範囲(代理権の範囲)を自分自身で決定することができる。
自分のメガネに適った支援者によって、自己が必要と考える支援を受けることができるもので、自己決定権により適合した後見制度といえるでしょう。
また、支援の範囲を必要な範囲に限れば「軽装備」の後見制度となり、全てのケースを法定後見で支援するより、社会全体のコストを抑えることできる。
任意後見は本人の自己決定権によりなった後見制度である。
「任意後見の限界」
取消権が無いため、消費者被害や不要・過大な商品購入等に対する対応策が乏しくなる。
このような事態に対しては、消費者契約法等の消費者保護法制や民法の詐欺・脅迫等の一般規定により対応することになります。
また、契約に基づく支援の提供であるため、本人の判断能力が低下した後は、支援の範囲の変更などを柔軟に行うことが難しいという問題がある。
なお、任意後見の開始は任意後見監督人の選任にかかっているので、適切な時期に選任の申立てがされるように担保しておかないと本人が保護されない状況が続くリスクがある。
「民事信託と任意後見の選択」
近時、後見制度の代替手段として家族信託(民事信託)が取り上げられることがあります。
信託は本人の意思に基づき設定されるので任意後見と競合する面があります。
家族信託の利用には、①受託者に適任者を得ることができるか?②信託は財産管理に対応するもので身上監護には対応できない。③受託者に対する公的な監督の仕組みがない。
という難点があります。
これらの問題をクリアできて家族信託の利用を検討することになるが、多額の資産を有する場合は、むしろ主要な財産については信託銀行と信託契約を締結し、身上面は任意後見を締結するという方法も提言されているようです。
「親亡き後のための任意後見の利用」
いわゆる「親亡き後」の子の財産管理手段として、親が健常なうちに障害のある子のために任意後見を準備しておくことが考えられます。
子に意思能力があれば、成年者の子は親の事実上の援助の下に、未成年者の子は親が同意をして、子が自己を本人とする任意後見契約を締結することができます。
しかし、成年者の子が意思能力がない場合には、任意後見契約は締結できません。
未成年者の子であれば、意思能力がなくとも、親が親権者として子を代理して子を本人とする任意後見契約を締結することが理論上は可能です。
しかし、「自分で後見人を選ぶ」という任意後見制度の趣旨から、あまりお勧めはできません。
任意後見受任者【相続手続きの相談窓口】
任意後見契約に関する法律第4条1項3号に定めている事由(未成年者や破産者など)に該当しない限りは、委任者(本人)は自由に受任者(他者)を選ぶことができます。
これが委任者(本人)の「自己決定の尊重」につながります。
法定後見では、後見人等になっているのは約72%が親族以外の司法書士や弁護士ですが、任意後見では友人や親戚でも構いません。
もちろん、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に任せることも可能です。
大切なことは、委任者(本人)自身が信頼できる人を選ぶことができるということです。
なお、任意後見受任者は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後には、任意後見人となります。
任意後見契約の変更・解除【相続手続きの相談窓口】
任意後見契約の解除は2つのパターンがあります。
①任意後見監督人が選任される前の解除
この場合、公証役場において、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。委任者(本人)からも、任意後見受任者からも、解除することができます。
②任意後見監督人が選任された後の解除
この場合、委任者(本人)も、任意後見人も、正当な理由(任意後見人の長期入院など)がある場合に限って、家庭裁判所の許可を受けて、任意後見契約を解除することができます。
任意後見事務の費用と報酬【相続手続きの相談窓口】
任意後見事務の処理に必要な費用は、委任者(本人)の財産から拠出します。
報酬については、身内が任意後見人となる場合は、無報酬の例が多いようですが、契約で報酬を定めることも可能です。
弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家に任意後見人を依頼する場合は、毎月定額の報酬を支払う旨を契約で定めることが一般的です。
これに対して、家庭裁判所が選任した任意後見監督人については、原則として報酬を支払わなければなりません。
任意後見監督人の報酬の金額に関しては、家庭裁判所が事案に応じて決定し、決定された報酬は委任者(本人)の財産から拠出します。

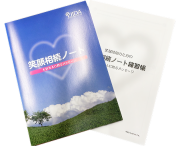 笑顔相続ノート・プレゼント!
笑顔相続ノート・プレゼント!