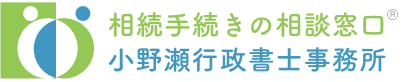不動産相続の事前対策が必要な理由【相続手続きの相談窓口】
【不動産相続の5つのポイント】
これからの時代は「何が」より「何のために」が物事のキーワードになりだしています。そこで、不動産相続における「何のため」を考えてみましょう。「何のため」は、遠い時間軸から始めなければなりません。その場合に、不動産相続や企業継承において考えておかなければならないポイントが5つあります。
①不動産や企業は原則として継続していく宿命を帯びているが、その所有者や経営者には寿命がある。
②不動産事業や企業経営は継承後の新しい所有者が意思決定を持つため、より戦略性が要求される。
③いずれのケースも利害関係者全員の未来の幸せ、そして、その結果として社会に役立たなければならない。
④どんな未来ビジョンがあるかを事前に示しておくべき姿勢が要求される。
⑤目先の損得より優先させるべきものを考えておかなければならない。
不動産相続や企業継承において考えておかなければならないことは、単に相続や継承という一時的な現象ではなく、人間と不動産、人間と企業という組み合わせが生じていることを理解しておくということです。土地という不動産は永遠であり、企業経営もゴーイングコンサーンと呼ばれる継続・永遠性が最大の目的となっています。
つまり、不動産や企業は永遠に存在していくべきものであるのに対し、所有、経営している人間には寿命があるということなのです。
当たり前のことですが、まず、この理解を明確にしておく必要があります。
簡単に言うと、不動産や企業には永続性が宿命付けられているのに対し、その司令塔たる人間には寿命があるため、相続や継承といった問題が発生するのだということです。単に相続や継承という一時点において上手にバトンタッチすることだけではより良い相続や継承にはなり得ず、常にその先にある未来を意識しておかなければならないのです。
【争族になりやすい不動産相続の8つの事情】
不動産相続には2つの課題があります。相続の前に「不動産」を付けているのは、相続の発生によりその後の所有者家系に大きな影響を与える可能性があるからです。
2つの課題とは「争族」と「相続」という2つになります。
「争族」=感情
不動産相続では人間の2つの側面が明確になるケースが多く発生します。1つは感情面であり、財産分割上における損得といった民法上の争いです。特に相続における平等主義は不動産の持つ帰属性に矛盾することが多く、こうした感情面のリスク対策を事前にしっかりまとめておく必要があります。
「相続」=勘定
勘定面の対策と匹敵するのが勘定面です。この勘定とは相続税のことです。相続税を支払うということは相続人にとっては債務を継承しているのと同じです。したがって、勘定面をクリアすることで、相続人間の利害は一致することとなるはずです。
相続税がどれくらいになり、その支払いは金融資産だけで賄うことは可能なのかについて事前に検証しておく必要があります。
「争族」という当て字を用いていますが、不動産相続は親族や相続人の間における争いの原因になりやすいケースと言えます。
反対に、預貯金などの金融資産が多い相続なら法定相続分で分割することも自由でありそもそも公平性を保ちやすい遺産でもあります。
ところが、不動産となるとそうはいきません。その主な理由は以下のようなことによります。
①不動産所有者は、不動産を所有・活用することで生計を立てている事業者的なケースが多い。
②不動産の相続税評価額は財産評価基本通達により路線価や倍率方式で計算されることにより、民法的分割(時価)を要求する相続人間で意見が一致しにくい。
③公平に分けようとすればするほど、不動産を処分して金銭化していくことになりがちである。
④不動産には住まいとしての役割、賃貸収益を生み出す役割、自らの事業地としての役割、将来設計としての役割などいくつもの顔がある。
⑤相続税法には物納という制度があるため、不動産の活用範囲が広くなる。
⑥誰がどの不動産を相続していくかは、不動産の立地特性と不動産相続人の組み合わせを明確にしておかなければならない。
⑦相続税法では、税制の仕組みによって土地の評価が大きく変動するため、こうしたメリットも考慮して相続人を決定していくことになりがちである。
⑧逆に、不動産が親の居住用しかない場合には、複数の相続人間で分割がしにくくなることで争いが起きやすい。
【見えざる債務の理解】
引き継いでいく不動産を処分することなく、相続税の納税に耐えうるかということです。
相続税とは「見えざる債務」のことです。金融機関からの借入金などを相続で引き継ぐ場合は、相続人は相当意識しているはずです。極端なことを言えば、プラスの財産は相続するが、借入金などのマイナスの財産は無くしてほしいと考えているはずです。
ところが、一定規模以上のプラスの財産だけが相続財産になると、相続税という実態のない債務が課税されることになるのです。したがって、相続税は「国からの借入金」であるという認識が必要になります。
いまだに「相続税なんて計算したこともない」という資産家はかなり存在しています。「金融機関からいくら借りているか知らない」と言っているのと同じであることに気付いていないのです。
また、金融機関からの借入なら数年以上の返済期日の中でしっかりとした金利交渉などを行い、返済原資を明確にして返済方法を決定していっているはずです。
ところが「国からの借入金」に対しては「いくら借入金が有るか知らない」は論外にしても、返済期限が10カ月であることを理解しておかなければなりません。
さらにこの10カ月のスタートは相続開始日(相続人が相続があったのを知った日)ですので、現実的には当初の2カ月程度は返済方法を考える余裕さえないでしょう。
もちろん、延納という制度がありますが、原則としては相続税の延納はやめた方がよいでしょう。もちろん出口戦略のある延納はかまいません。
【不動産相続戦略のカギ】
何のために不動産を相続するのか、あるいは、何のために企業経営を引き継ぐのかが明確になっているかどうかという視点です。相続税が大変だから節税するのも結構ですが、そのためには「何のために節税するのか」が明確になっていなければなりません。
さらに、単に明確になっているのではなく、その明確になっている理由に「社会性はあるか」がより重要になります。社会性があることにより、社会がその「何のために」にすることをバックアップしてくれるからです。支援者が多いケースと嫉妬ややっかみなどを意識しなければならないケースでは、どちらが成功する確率が高いかは自明の理です。この場合の成功も、うまくいったとか、とりあえず納得しあえたといった目先の成功ではありません。
不動産を所有することで親族が互いの未来の幸せを分かち合い、企業が継続してくことで社会に様々なお役立ちを提供できるといったことが続いていくという長期にわたる成功の仕組みすくりが必要だということです。
【不動産という資産に対するコスト把握】
不動産は所有していることでコスト負担が生じています。このコストは単なる現状コストのことではなく、これから発生するであろう未来コストも含んでいます。
未来コストとは大きく分けて2つあります。
①近い将来必ず発生するであろう大規模修繕などのコスト
②近い将来発生する相続税の納税コスト及び相続の発生に関する不動産移転コスト
①②の近い将来とは、少なくても10年くらいのスパンで考えておくべきです。
現状のバランスシートには表現されていないため、未来コストというわけです。こうした「見えないコストを見えるかすることがリスクマネジメント」であり、戦略的な不動産活用につながってきます。
「見える化」することで人間は意識が高まってきます。そのため、対応法が具体的になります。まさにリスクマネジメントなのです。
不動産は本当に資産としての不動産なのでしょうか。こうした一連の「見える化」によって個々の不動産の価値を再チェックしていかなければなりません。資産としての不動産は負債としての未来コストを差し引いても本当に必要な資産なのかどうかを検討していかなければなりません。
【3つしかない節税戦略】
節税戦略とは、「何のために相続税を軽減するのか」という質問にたいして納得できる解答を引き出せるかどうかといった方がわかりやすいでしょう。
「節税してどうするのですか」に対する解答が、長期的、空間的な広がりの中から見つけられているかどうかということです。
相続税の節税戦略は3つしかありません。
①資産(特に土地など不動産)の評価減
②資産の移転(贈与・寄付・消費)
③法定相続人(相続税法上の法定相続人)の数
その中の③に関しては、節税のためというより感情や心情面に配慮した結果が節税につながったという程度のことです。
実質的には①評価減と②移転の2つしかないことになります。
この評価減と移転を考えるにあたっては、以下のようなポイントをクリアしなければなりません。
「評価減」⇒価値を下げないで評価をさげることの発想力
「移 転」⇒社会軸と未来軸の広げられる範囲の確認
【評価減の基本は本来の不動産価値を下げないこと】
評価減の基本的な考え方である「価値を下げないで評価を下げる」とは、収益力や財産価値そのものは現状を守りながら(あるいは、現状より高めながら)相続税の対象となる相続財産評価を下げることを言います。不動産の評価の下げ方には以下の4つのパターンがあります。
1,立地的要素
立地的な要素は、さらに見える欠陥と見えない欠陥に分けられます。
見える欠陥には、不整形地、無道路地、傾斜地、温湿地、凸凹地、がけ地、三角地、間口狭小地、道路との高低差などが入ります。
見えない欠陥には、土壌内の欠陥のことで、土壌汚染、埋蔵物、津波による塩害、放射能汚染地、上下水道・ガスなどの埋設管の有無などが考えられます。
2,環境的要因
環境的要因とは、隣地が墓地とか工場やごみ処理施設の臭気が強い、あるいは、近くに高速道路や鉄道の高架があり日照や騒音障害が生じているケースのことを言います。
3,心理的要素
心理的な要素とは、その土地や建物の時価を判定するために影響力のある状況が生まれているということです。例えば、境界の争いがある土地や自殺されていたマンションの1室、あるいは、暴力団事務所が入居しているビルなども心理的要因となるでしょう。
要するに、「いわくつき物件」は実際の取引価格も大幅に減少するということです。
4,法律的要素
法律上の要素とは、①税法上、②相続人、③公法上、④災害法などです。
税法上とは利用単位・種類区分によるもので、私道、貸宅地、貸家建付地による評価減のことです。また、相続人の要素には小規模宅地等の評価減、公法上には建築基準法42条2項道路(セットバックが必要な土地)や都市計画道路の予定地なども入ります。
東日本大震災などのケースでは、土地は震災特別法、建物は災害減免などによって評価減の対象となっています。
上記のいずれも不動産を活用して収益を上げる場合にはデメリットになります。これが逆に不動産相続における不動産の評価にとっては評価減として活用できるわけです。

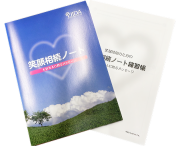 笑顔相続ノート・プレゼント!
笑顔相続ノート・プレゼント!