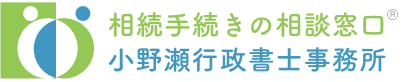相続税の計算の仕方
相続税シュミレーションを自分で行う参考にしてください。
①正味の遺産額を算出する
=土地建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたもの
例)相続人:妻・長男・長女
相続財産:
現金・預金=4,000万円
土地・建物=2,000万円(厳密には財産評価を要します。固定資産税納税通知書の評価額で計算)
生命保険金=4,500万円
(受取額6,000万円ー控除500万円×3人)
借入金 =△500万円
葬儀費用 =△200万円
4,000万円+2,000万円+4,500万円ー500万円ー200万円=9,800万円
正味の遺産額=9,800万円
②課税遺産総額を算出する
=正味の遺産額から基礎控除を引いたもの(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
正味の遺産額=9,800万円
基礎控除額 =4,800万円
(3,000万円+600万円×3人)
課税遺産総額
9,800万円ー4,800万円=5,000万円
③法定相続分で課税遺産額を按分し、相続税額を計算
法定相続分:妻1/2・長男1/4・長女1/4
妻
遺産の按分:5,000万円×1/2=2,500万円
相続税額:2,500万円×15%-控除50万円=325万円
長男・長女
遺産の按分:5,000万円×1/4=1,250万円(各人)
相続税額:1,250万円×15%-控除50万円=137.5万円(各人)
相続税総額:600万円
(325万円+137.5万円+137.5万円)
④実際の遺産按分比率で相続税額を按分
例)妻:5,800万円分の遺産を相続
長男:2,940万円分の遺産を相続
長女:980万円分の遺産を相続
㋐妻の相続税額
600万円×5,800万円/9,800万円=360万円
※ただし、配偶者控除で妻に掛かる相続税=0円
㋑長男の相続税額
600万円×2,940万円/9,800万円=180万円
㋒長女の相続税額
600万円×980万円/9,800万円=60万円
となります。
相続税額の計算は正確には税理士に依頼すれば間違いはありませんが、シュミレーション的に計算したい場合はご自分でも可能かと思います。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは簡単に説明すると「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険金などの財産のこと」です。
みなし相続財産は少し特殊で、相続放棄をした人も相続することができます。
みなし相続財産の代表例2つ
①亡くなった時に受け取る「生命保険金」
被相続人が亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」は相続財産とみなされます。
ただ、生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。
| 被保険者 |
保険料負担者 |
保険金受取 |
税金の種類 |
| 被相続人 |
被相続人 |
相続人① |
相続税
(満期時は贈与税) |
| 被相続人 |
相続人① |
相続人① |
所得税・住民税 |
| 被相続人 |
相続人① |
相続人② |
贈与税 |
②亡くなった時に勤務先から支払われる「死亡退職金」
相続税がかかる死亡退職金の範囲は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
| 退職金を受け取る時期 |
税目 |
| 生前に本人が受け取った退職金 |
所得税 |
| 死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金 |
相続税 |
| 死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 |
所得税(一時所得) |
みなし相続財産の4つの知識
①みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。みなし相続財産は厳密に言うと本来は相続財産ではないからです。相続がきっかけで取得する財産です。
そのため、相続放棄をしていても受取人になっていればみなし相続財産を受け取ることができます。
ただし、相続放棄をしている場合、下記で説明する「非課税枠」の使用ができず、相続税が課税されるため注意が必要です。
②みなし相続財産は相続人が「生命保険金」と「死亡退職金」を受け取る場合に限り一定額までは非課税となっています。
| 生命保険金非課税限度額 |
500万円×相続人の数 |
| 死亡退職金非課税限度額 |
500万円×相続人の数 |
相続人ではない人が被相続人の生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税枠の対象外となるため注意が必要です。
③みなし相続財産は基本的に遺産分割の対象外です。
みなし相続財産は受取人が指定されており、受取人固有の財産と考えられるからです。
そのため、みなし相続財産は、相続人同士で遺産の相続配分を決める話し合いである遺産分割協議の対象にはなりません。
④「生命保険金の非課税枠」を利用して節税対策に利用されるケースがあります。
みなし相続財産を利用した節税対策を簡単に説明すると「最大限非課税となる金額を保険料として支払い、亡くなった時に支払った保険金を受け取る」というものです。
その他のみなし相続財産
□年金や保険金などを定期的に受け取る権利である「定期金の権利」はみなし相続財産として扱われます。
□生命保険料の支払いを亡くなった被相続人が負担していた場合に自分が契約している生命保険を解約することにより発生する「解約返戻金」や、生命保険の契約を続行して発生する「満期保険金」を受け取れる権利である「生命保険契約に関する権利」
□遺言により債務を無償で免除された場合や、著しく低い価格で債務を免除された場合、その免除された債務の金額に相当する金額がみなし相続財産として扱われます。
例えば、被相続人に700万円を借りていたが、遺言によって返さなくてもよくなった場合がこれにあたります。
この場合の相続税は支払いが免除された700万円に対して課税されることになります。
生前贈与の活用1(暦年贈与の活用)
生前贈与とは、生きている間に財産を他人に無償であげることをいいます。
贈与には贈与税がかかります。
贈与税の計算式
贈与税=(贈与財産価格ー基礎控除110万円)×税率ー控除額
㋐その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与価格を合計する
㋑その合計額から基礎控除額110万円を差し引く
㋒差し引いた後の金額に税率を乗じて計算
上記を見てわかるように贈与税には基礎控除額(110万円)があります。
その基礎控除額以内の贈与には贈与税は掛かりませんので、毎年110万円までの贈与を積み重ねる方法があります。
コツコツ贈与を積重ねて相続財産を減らして相続税を減らしたり、納税資金を準備することに有効です。
良く間違う人がいるのは、1人から110万円受け取って、他の人からも110万円受け取っても贈与税が課税されないということではありません。
2人から合計220万円贈与を受けていますので、220-110=110万円に贈与税が課税されます。
あくまで受贈者からみた1年間の贈与額です。
生前贈与の活用2(相続時精算課税制度・居住用不動産の配偶者控除)
生前贈与の活用で取り上げられる有名な二つの制度です。
1⃣相続時精算課税制度の活用
通常の暦年贈与では毎年110万円まで非課税ですが、この制度を使えば、累計2,500万円まで贈与税がかからずに子や孫に贈与できます。
最終的には相続時に遺産に組み込まれて相続税の課税がされます。
ただ、今後値上がりが想定される不動産や株式を贈与すると、贈与時の評価額で確定できる効果があります。
また、収益不動産を子に贈与することにより、贈与以後の賃料収入は子の所得になるので、親の所得税対策と遺産の増加抑制効果もあります。
相続時精算課税制度を選択できる条件
①贈与者:60歳以上の父母又は祖父母
②受贈者:20歳以上の子や孫
相続時精算課税制度を選択すると
①特別控除額累計が2,500万円まで非課税
②累計2,500万円超えた部分に対して、一律20%で課税
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
相続時に課税
㋐贈与財産の価格を相続財産に加算して、相続税額を計算
㋑既払いの贈与税額がある場合、相続税額から控除する
㋒控除しきれない金額は還付可能
相続時課税制度のデメリットとリスク
Ⓐ小規模宅地の評価減の特例が使えなくなる
Ⓑ相続時に物納ができなくなる
Ⓒ不動産に関するコストが高くなる(不動産を贈与すると不動産取得税が発生、登記の登録免許税が相続より高い)
Ⓓ同じ贈与者からの新たな贈与に暦年贈与(基礎控除110万円)が使えなくなる
2⃣居住用不動産の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭の贈与をする場合、2,110万円(2,000万円+基礎控除110万円)まで贈与税がかからない。
注意点
そもそも配偶者の死亡によりその相手側が遺産をもらう場合1億6,000万円または遺産の半分まで相続税は掛かりません。
自宅を夫婦共有にすることにより、将来夫婦で高齢化した際に認知症による売却不能リスクが二人分になってしまうことに注意です。
不動産の相続税評価額
相続税法は、遺産の価格は原則「時価」とされていますが、現金以外では時価を定めることが難しいケースも多いのです。
特に不動産の中でも土地は1物4価とか1物5価なんていわれるだけに難しいので、「財産評価基本通達」によって以下のように定められています。
土地:「路線価方式」または「倍率方式」
「路線価方式」とは
国税庁のサイトに相続税路線価があり、評価したい土地が接している道路に1㎡当たりの価格が記載されています。
その価格を地積に乗じて、奥行き補正などの補正値を乗じた価格を評価額とすることです。
「倍率方式」とは
固定資産税評価額に国税庁のサイトに記載されている対象地の倍率を乗じた価格とすることです。
借地:自用地評価×借地権割合
借地権割合も国税庁のサイトの相続税路線価を見ると記載されています。対象地の接している道路に借地権割合の記号で判断します。
建物:建物の固定資産税評価額
小規模宅地の評価減の特例
不動産の中で土地は1物4価なんて言われており複雑なため、相続税評価額は「財産評価基本通達」で定められているのですが、1物4価とは何でしょう?
一般的には、以下のような4つの価額があります。
流通価額:市場で取引されている価格
公示価額:流通価格の90~95%くらいの価格
相続税評価額:公示価格の80%くらいの価格
固定資産税評価額:公示価格の70%くらいの価格
土地の相続税評価額は上記の中で相続税路線価で計算するのです。
ですから、現金1億円は相続税評価額も1億円ですが、土地は1億円で流通するものであっても相続税評価額は7,500万円くらいになります。
その流通価格と相続税評価額の違いを利用して遺産総額を減らすための相続対策では不動産が良く使われます。
さて、土地については土地というだけで財産評価額は減ることになりますが、さらなる特例もあって相続税対策には重要です。
それが「小規模宅地の評価減の特例」です。
大まかな内容が以下の表です。
小規模宅地の評価減の特例
| 区分 |
限度面積 |
評価減の割合 |
大まかな要件 |
| 特定居住用宅地等 |
330㎡ |
80% |
配偶者や同居の親族が取得 |
| 賃付事業用の宅地等 |
200㎡ |
50% |
賃貸事業の継続 |
| 特定事業用宅地等 |
400㎡ |
80% |
事業の継続 |
実はこの特例は細かい適用条件があります。
前提条件として
①被相続人又は被相続人と同じ財布で生活していた親族(専門用語で生計一親族と言います)(以下、この2つを合わせて「被相続人等」と言います)の事業又は居住の用に供されていた宅地等(土地だけでなく借地権等も含みます)であること②その宅地等が建物又は構築物の敷地であること
次に宅地の種類と取得者の要件
【特定居住用宅地等】
被相続人等が住んでいた宅地の要件です。被相続人が住んでいた宅地と被相続人の生計一親族が住んでいた宅地の2つに分けて要件を確認します。
a.被相続人が住んでいた宅地
下記に掲げる人が相続した場合のみ適用があります。
㋑被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
㋺被相続人と同居していた親族(居住要件、所有要件共にあり)
㋩被相続人と同居していないが下記要件を満たす親族(所有要件のみあり)
・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人と同居している相続人がいないこと
・被相続人が亡くなる前3年間、日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと(いわゆる「家なき子」)
b.被相続人の生計一親族が住んでいた宅地
下記に掲げる人が相続した場合のみ適用があります。
㋑被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
㋺被相続人の生計一親族(居住要件、所有要件共にあり)
【貸付事業用宅地等】
被相続人等(生計一親族も含みます)が貸付事業をしていた宅地の要件です。
㋑事業継続要件
被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、貸付事業を申告期限まで継続すること
㋺保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること
【特定事業用宅地等】
被相続人等(生計一親族も含みます)が事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地の要件です。こちらは、特定居住用宅地等よりは要件が簡易的で、下記の2つの要件となります。
㋑事業継続要件
被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、事業を申告期限まで継続すること
㋺保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること

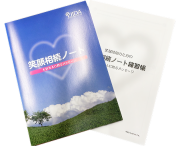 笑顔相続ノート・プレゼント!
笑顔相続ノート・プレゼント!